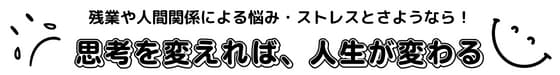『6-12.プロジェクトを成功に導く秘訣(11)私心を捨てて、献身的になる』の記事では、
- 私心を捨てて、自社、自部門、自分の利益を優先することなく、社内、社外含めた関係者全員の全体最適を考えて、ゴールの達成に献身的になって欲しいこと
- 「私心を捨てて、献身的になる」ことで、プロジェクト期間中はもちろん、プロジェクト後でも良い協力関係を築き、より大きな成果を残して欲しいこと
をお伝えしました。
今回の記事も含めて、具体的に『プロジェクトを成功に導く秘訣』について、詳しく解説しますので、あなたが日常生活で、仕事をするうえで、「使える!」と思ったものは、どんどん実践してみてください!
『プロジェクトを成功に導く秘訣』の12個目は、
・やってみせてから、やらせる
です。

プロジェクトは、複数人で協力して同じゴールを目指す活動であり、複数人で納得感を高めて意思決定する方法、計画の立て方、課題解決のやり方、コミュニケーションの取り方など、定常業務ではなかなか経験できないことを学べる、人を成長させるには、最高の場となります!
「やってみせてから、やらせる」とは?
「やってみせてから、やらせる」とは?
- プロジェクトを通じて、人を成長させること
- 成長させたい人を、意図的に選ぶこと
- 人を成長させるには、やってみせてから、やらせること
です。
プロジェクトを通じて、人を成長させること
プロジェクトは、複数人で協力して同じゴールを目指す活動です。
『6-1.なぜ、「プロジェクト」を成功させることは難しいのか?』の記事にも書いているのですが、
プロジェクトには、
- 期限がある(余裕を感じれる期限ではない!)
- 不確実性がつきものである(どれだけ準備しても、予期せぬことが起こる!)
- 全く同じものが一つとしてない(毎回、前提条件が異なる!)
- 利害関係者が多い(みんなそれぞれの立場で、好き勝手なことを言う!)
ので、一つとして簡単にゴールを達成できるものはありません。
複数人で協力して、
- 意思決定を次々に行うこと(誰もが納得できる選択を行うこと)
- 計画を立てて実行すること(最も効率が良いスケジュールを計画すること)
- 効率良く、効果的に課題を解決すること(優先順位を決めて課題に取り組むこと)
- 意図的にコミュニケーションを取ること(良い協力関係を築けるようにすること)
が求められるので、プロジェクトを通じて、多くの気づきや学びを得ることができます。

複数人で協力して、プロジェクトを完遂させることは、決して簡単なことではありませんが、簡単ではないからこそ、プロジェクトは、人を成長させる最高の場となっているので、プロジェクトを通じて、人を大きく成長させることができます!
成長させたい人を、意図的に選ぶこと
プロジェクトを通じて、人を成長させるためにも、まずは、「成長させたい人を、意図的に選ぶこと」が大切です。
成長させたい人を、意図的に選ぶ際は、
- 学ぶことに意欲的な人
- 変化に柔軟に対応できる人
- 会社の将来を担う若手
を選ぶことをオススメします!
プロジェクトでは、多くの気づきや学びを得ることが出来ますが、そもそもその人に「学びたい意欲」がなければ、得られる気づきや学びは半減してしまいます。
「学びたい意欲」を確認するためにも、プロジェクトメンバーは、公募することがオススメで、公募に対して、自ら手を挙げることが、「学びたい意欲」の一つの現れとなります。
また、プロジェクトは、「不確実性がつきものである」「利害関係者が多い」ので、次々と起こる予期せぬ事態に対して、たくさんの関係者から好き勝手に言われる意見に対して、柔軟に対応することが求められます。
「変化に柔軟に対応できるかどうか」は、普段から、
- 新しいことに積極的に取り組んでいるか?
- 周りの人の意見に耳を傾けているか?
を観察することで分かります。
そして、会社の将来を担うのは、若手の社員です。
若手の社員ほど、「学びたい意欲」があり「変化に柔軟に対応できる」人も多いので、人を成長させる最高の場であるプロジェクトには、ぜひ、若手を積極的に起用することをオススメします!

従来の会社のやり方を抜本的に変えるような、社内の基幹システムを刷新するような大きなプロジェクトは、10年単位でも1度あるかないか分からないぐらい貴重な成長の機会なので、ぜひ、会社の将来を担う若手の社員を抜擢してください!
人を成長させるには、やってみせてから、やらせること
プロジェクトに「成長させたい人を、意図的に選ぶこと」ができたら、実際のプロジェクト現場において、どんどん「やってみせてから、やらせること」が大切です。
プロジェクトに初めて参画するメンバーは、プロジェクトの進め方、立ち振る舞い方、抑えるべき点などが分からない状態なので、まずは、しっかりとお手本を見せることです。
お手本を見せた後に、
- どのような意図で行ったのか?
- 何がポイントであったのか?
- どんな準備が必要であったか?
など、やってみせたことに対する裏側の解説を行います。
裏側の解説まで済ませてから、実際に「やらせること」、そして、やったことに対する「振り返りをすること」で、一歩ずつ着実に、成長させることができます。

プロジェクトは、普段の定常業務とは進め方が異なるので、いきなり一人でやらせるのは酷です。必ず「やってみせて(裏側の解説までして)から、やらせる」こと、そして、やらせたことの振り返りをして少しずつ成長させることが大切です!
なぜ、「やってみせてから、やらせる」ことが大切なのか?
なぜ、「やってみせてから、やらせる」ことが大切なのか?というと、
- 座学や研修では、学びに限界があるから
- やってみせてから、やらせることが、人を育てる鉄則だから
です。
座学や研修では、学びに限界があるから
座学や研修でも、一定の効果は得られますが、どうしても学びに限界があります。
座学や研修では、
- 机上の空論になりがちで、べき論だけでは解決できない課題に対処できない、、、
- 「似てる」と言っても実際の現場ではないので、「自分ごと化」しにくい、、、
- 座学や研修で学んだことをいきなりやれと言われても、なかなかできない、、、
のが現実です。
座学や研修にて、「こうするべき」「こうあるべき」というべき論を学ぶことも、確かに重要ですが、実際の現場では、べき論だけでは解決できない課題もたくさんあります。
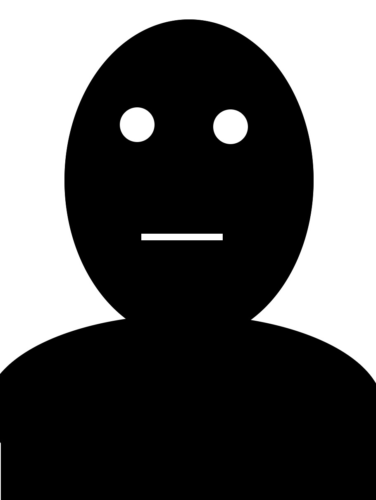
「言うべきことは分かるけど、伝え方が難しい、、、」「すべきことは分かるけど、期限や予算の制限があるから、全部はできない、、、」
など、べき論は分かっていても、実行できない(したくてもできない)ことが、存在します、、、
例えば、社外で立場も年齢も上の人に対して、言うべきことは言わないといけないが、

「言うべきことをどこまで言うか?」「どのタイミングでどのように伝えるか?」「どうすれば、お互いの納得感を生むことができるか?」
山積みの課題に対して、優先順位を決めて1つ1つ解決していくしかないが、

「どのように優先順位をつけるか?」「どこまでプロジェクト期間内に対応するか?」「どうすれば予算内に収めることができるか?」
など、べき論だけでは解決できない課題の対処方法は、現場でしか学べません。
座学や研修では、様々なケースの事例を用意しており、現場と「似てる」事例を学ぶことができますが、「似てる」と言っても実際の現場ではないので、
そっくりそのまま使える訳でもなく、責任を伴う訳でもないので、どうしても「自分ごと化」しにくいものです。
実際の現場では、期限や予算を超過したら、お客様に迷惑が掛かってしまいます。
お客様の期待に応えることができなければ、対価をもらうことができない可能性もありますし、当然、次の仕事ももらえず、関係も途絶えてしまう場合もあります。
実際の現場では、すべての行動に責任が伴いますので、座学や研修とは、真剣度合いが全く異なります。
また、座学や研修で学んだことを、実際の現場でいきなりやれと言われても、なかなかできるものではありません。
普通は、
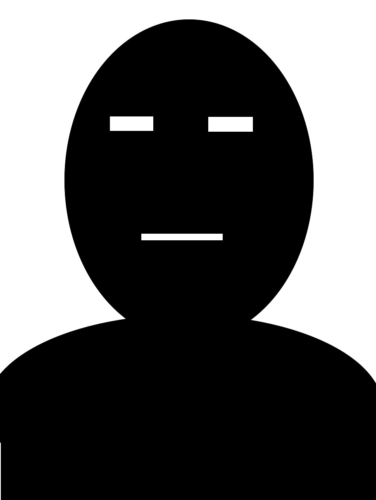
「いやいや、座学や研修と状況違うし、、、」「座学や研修で学んだことを、どのようなさじ加減で使ったら良いか分からへんし、、、」「というか、まずは、やってみせてよ、、、」
となります。

どうしても座学や研修では、学びに限界がありますので、すべての行動に責任が伴う実際の現場で、座学や研修で学んだことを「どのように実践すれば良いのか?」一度、やってみせてから、次に、本人にやらせることが大切です!
やってみせてから、やらせることが、人を育てる鉄則だから
人を育てるには、「やってみせてから、やらせること」が鉄則です。
私が人を育てる際に、いつも肝に銘じているのは、
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
という、山本五十六さんの格言です。
プロジェクトに通じるのは当然ですが、現在でも、ありとあらゆる場面で、人を育てる際に通じる格言と言えます。

かなり有名な格言中の格言なので、人に何かを教える前に、人を育てる前に、毎回、この格言を復唱することをオススメします! 私は、この格言が書かれたマウスパットを使っているので、毎日、復唱しています! もう、十年以上前に買ったので、マウスパットはボロボロですが、、、(笑)
どのように、「やってみせてから、やらせる」と良いのか?
どのように、「やってみせてから、やらせる」と良いのか?というと、
- まずは、会議から実践する
- その場でフィードバックする
- 挑戦することを楽しませる
と良いです。
まずは、会議から実践する
プロジェクトは、意思決定の連続であり、その意思決定のほとんどは、関係者で会議をして決めることになります。
いわば、会議は、プロジェクトの縮図です。
一つ一つの会議の質が、プロジェクトの意思決定の質になり、プロジェクトのゴールを達成できるかどうかを大きく左右する要因となります。
会議で結論が出なければ、プロジェクト全体が遅延してしまいます。
会議を円滑に進めることは、プロジェクトを円滑に進めることと言っても過言ではありません。
プロジェクトでは、下記の「4つのP」
- Purpose:目的が定まっていること
- Process:到達するための道すじが明確になっていること
- Property:装備品、必要な道具が明確になっていること
- People:メンバーと体制が明確になっていること
が重要となりますが、会議でも「4つのP」
- Purpose:何のために会議をするのか?その会議では、何を達成できれば良いのか?
- Process:目的とゴールを達成するために、何をどういう順番に議論すれば良いのか?
- Property:議論を円滑に進めるために、どこでどんな設備やツールを使うと良いのか?
- People:その会議で意思決定を行うには、誰に参加してもらう必要があるのか?
が重要となります。
会議で、時間内に、関係者間で円滑に議論を行い、納得のいく意思決定を行うには、しっかりした準備が必要です。
行き当たりばったりで会議をしても、何の準備もせずに議論をしても、関係者間で合意するのに必要な人を抜きにしてどれだけ話をしても、納得感の高い意思決定を行うことはできません。
「やってみせる」際は、「どうすれば、納得感の高い意思決定ができるのか?」のお手本を見せる必要があります。
「やってみせた」後に、「どんな準備をして、どんなことに気を付けて実行したのか?」の裏側を説明します。
そして、「やってみせて(更に裏側を説明して)から」、成長させたいメンバーに、会議の準備から、会議で納得感の高い意思決定を行うまでのすべてを「やらせる」ことが大切です。

プロジェクトは意思決定の連続であり、すなわち、会議の連続です! 1つ1つの会議の質を高めることが、プロジェクトゴールを達成することに直結するので、会議を人を成長させる最高の場として有効活用し、複数人で納得感の高い意思決定ができるようになるスキルを身に着けてもらうことが大切です!
その場でフィードバックする
「やってみせてから、やらせる」を実施した後は、「その場でフィードバックする」ことが大切です。
フィードバックは、「短くても良いので、すぐにやること」が何より重要で、
時間があけばあくほど、やった内容を忘れてしまいますし、その時の感情も冷めてしまいます。

「よっしゃ、●●はうまくできた!」
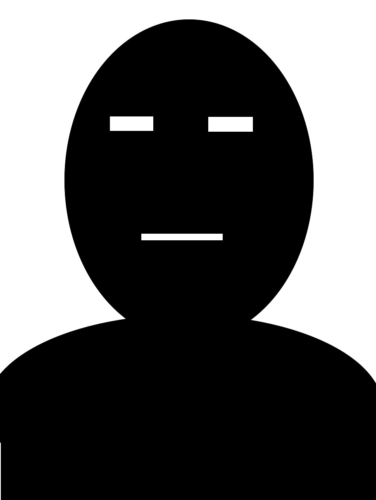
「あぁ、▲▲はできなかった、、、」
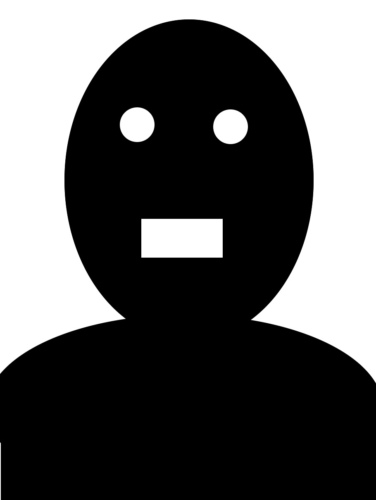
「次回は、■■してみよう!」
というように、感情が強く残っている会議が終わった直後の熱量(感情)で実施することが大切です。
熱(感情)が冷めた後にフィードバックを行っても、良かったことも、悪かったことも、次に活かしにくくなります、、、。
「その場でフィードバックする」際のポイントは、
- 「良かったこと」と「改善点」を本人から聞くこと
- 客観的に見て感じたことを、ありのままの事実として伝えること
- 「次、どうするか?」を本人から聞くこと
です。
「良かったこと」と「改善点」を本人から聞くこと
実際に、「やってみた」直後に、本人の口から
- 外から見ているのと、実際に「やる」のでは、何が違ったか?
- 実際に「やってみて」良かったことは何か?できたことは何か?
- 逆に「やってみて」できなかったことは何か?改善すべきことは何か?
を聞くことが大切です。
まずは、しっかりと自分の頭で考えて、自分で「良かったこと」「改善点」を見つけて、自分自身を向上させることが重要です。

フィードバックは、短くても良いので、会議などを「やらせてみた」直後にやることが何より重要で、直後は、本人も「良かったこと」「改善点」を強く覚えているので、まずは、本人の考えをすべて吐き出してもらうことが大切です!
実際に「やってみて」良かったことは何か?できたことは何か?
次に、「やらせてみた」直後に、「やった」本人に対して、客観的に見て感じたことを、ありのままの事実として
- ●●の説明しているとき、▲▲さんが、悩ましい顔してたわ!何か懸念があるかも、、、
- ■■が長くなったから、××の議論の時間が少なかったね。皆ちょっと不服そう、、、
- ○○さんの意見サラっと流したけど、少し気になったわ。どう思う?
などと伝えることが大切です。
納得感の高い意思決定を行うのに、「これしかダメ!」というような正解はないので、「あれがダメ!」「こうせなダメ!」というような指摘より、客観的に見て感じたことを、ありのままの事実として伝えることで、更に、納得感の高い意思決定を行うための創意工夫をしてもらう方が良いです。

教える側は、ついつい「こうしないとダメ!」と言ってしまいがちですが、一番大切なことは、自分自身で考えて、改善を繰り返して、自ら成長してもらうことなので、正解を押し付けるのではなく、客観的事実を伝えることが大切です!
「次、どうするか?」を本人から聞くこと
そして、自分で考えてもらい、こちらからも客観的な事実を伝えた後に、再度、本人に「次、どうするか?」を聞き
- 次は、参加者の表情も気にして、疑問が浮かんでいそうな場合は、その場で確認します!
- 次は、より円滑に進めるためにも、■■の準備にもっと時間をかけます!
- ○○さんの意見は確かに気になるので、直接本人に、真意を確認してみます!
など、次に取るべき行動を確認し、頭の中を整理した状態(スッキリした状態)にすることが大切です。

頭の中が整理されていない状態(何かモヤモヤしている状態)で、次の仕事をしてしまうと、その次の仕事にも悪い影響を及ぼしてしまうので、「やらせた」後は、その場でフィードバックして、その場で頭をクリアにすることが重要です!
挑戦することを楽しませる
「やってみせてから、やらせる」ことの大前提として、「挑戦することを楽しませる」ことが大切です。
何事も
- 自分で挑戦するからこそ、「気づき」や「学び」がある
- 「気づき」や「学び」があるからこそ、成長を実感できる
- 成長を実感できるからこそ、やっていて楽しい!
ものです。
プロジェクトは、ゴールを達成するのが難しく、多くの関係者間で、納得感の高い意思決定を行うのも難しいものです。
困難な課題に直面したり、予期せぬ事態が起こったり、急な計画変更への対応を迫られたりしますので、プロジェクト途中では、小さな失敗を山ほどします。
そして、失敗すればするほど、「気づき」や「学び」が多く得られます。
むしろ、失敗してナンボです。(「失敗してこそ、得られるものがある」という意味です)
小さな失敗から「気づき」や「学び」を得て成長し、関係者と協力しながら、致命的な失敗を回避して、試行錯誤しながら、プロジェクトのゴールを達成することが大切です。
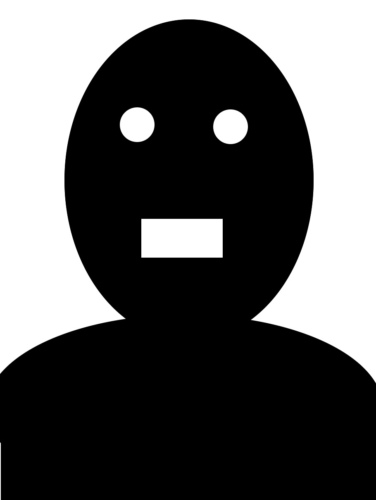
でも、どうやったら、育てたい人に「挑戦することを楽しませる」ことができるの!?
と思われたかもしれませんが、
それこそ、「やってみせてから、やらせる」ことです。
つまり、育てたい人に「挑戦することを楽しませる」前に、自分自身が、「心から挑戦することを楽しむ」お手本を見せることです。
育てたい人に対して、
- 今日は、役員に対するプレゼンやから、気合入れて行くわ!ゴールは予算承認されること!
(プレゼン終了後に)
- あぁ、●●が未解決やから、予算承認されんかった!あと、少しやったのに、、、。
- けど、大枠は認めてもらえた。あとは、●●の解決に全力を尽くして、再トライやわ!
- ●●の解決するために、まずは、データ調べて、次に、▲▲さんに話を聞くか!
など、実際に、挑戦して、失敗から貪欲に学び、楽しみながら試行錯誤する姿を見せることが大切で、その姿を見せることができれば、育てたい人に「挑戦することを楽しませる」ことができます。

「挑戦することを楽しませる」こと自体も、「やってみせてから、やらせる」ことが大切なので、ぜひ、あなたの「挑戦することを楽しむ姿」を、あなたの「生き様」を、ありありと成長させたい人に見せつけてあげてください!
まとめ
- プロジェクトは、人を成長させる最高の場なので、成長させたい人を、意図的に選ぶこと
- 人を育てるには、「やってみせて(更に、裏側を説明して)から、やらせる」こと
- 「やらせた」後は、短くても良いので、すぐにフィードバックすること
「人を育てよう!」と思うと、ハードルが高く感じますが、「人を育てながら、自分も育とう!」「やってみせて、ダメな点はその場で改善しよう!」と思えば、人を育てることに対するハードルは低くなります。
プロジェクトは人を育てる最高の場なので、成長させたい人と一緒に、あなた自身も大きく育つことで、あなたの人生がより良いものになることを、心から願っています!