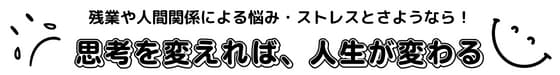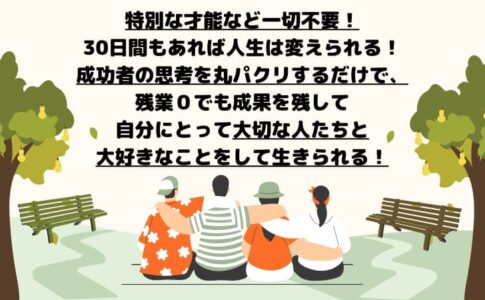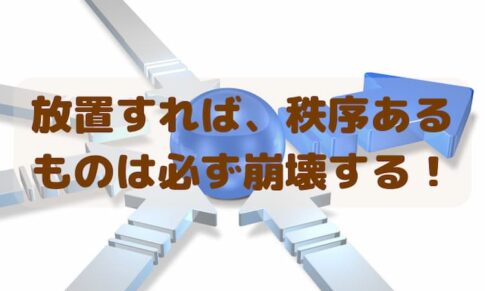『6-19.プロジェクトを成功に導く秘訣(18)プロトタイプを作成する』の記事では、
- 「何かを作る」際は、完成品の前に、必ず試作品(プロトタイプ)を作り、関係者間で意見を出し合い、認識を合わせて、完成品に反映させて欲しいこと
- 「プロトタイプを作成する」ために、便利なハードウェア・ソフトウェアなど使えるものは何でも使って欲しいこと、また、紙での出力でも良いので試作品を作って欲しいこと
をお伝えしました。
今回の記事も含めて、具体的に『プロジェクトを成功に導く秘訣』について、詳しく解説しますので、あなたが日常生活で、仕事をするうえで、「使える!」と思ったものは、どんどん実践してみてください!
『プロジェクトを成功に導く秘訣』の19個目は、
・『7つの習慣』に従う
です。

『7つの習慣』に従うことは、『1-7.思考を変え人生を変える方法(7)この人の思考になれたら、人生は好転する』の記事で紹介した「加藤 将太さん」が実践している秘訣です。加藤さんは、人と協力して何かを成し遂げる際には、必ず、『7つの習慣』に従うことが大切と言われています!
目次
『7つの習慣』に従うとは?
スティーブン・R・コヴィー氏が、著書『7つの習慣』で提唱する『7つの習慣』のうち、
- 第一の習慣:主体性を発揮する
- 第二の習慣:目的を持って始める
- 第三の習慣:重要事項を優先する
までは、「私的成功」を主目的として書かれていますが、
(第一の習慣は、プロジェクトでも大切なので、『6-11.プロジェクトを成功に導く秘訣(10)一人一人が「主体性」を発揮する』にて、記事にしています)
- 第四の習慣:Win-Winを考える
- 第五の習慣:理解してから理解される
- 第六の習慣:相乗効果を発揮する
に関しては、「公的成功」を主目的として書かれており、複数人で効果的に協力し、あらゆる課題を解決して、ゴールを達成するカギになるものです。
- 第七の習慣:刃を研ぐ
に関しては、日々の生活で自己を高めることを目的として書かれており、「私的成功」「公的成功」のどちらにおいても重要となります。
本記事において、『7つの習慣』に従うとは、
複数人で効果的に協力し、あらゆる課題を解決して、ゴールを達成するカギになる
- 第五の習慣:理解してから理解される
- 第四の習慣:Win-Winを考える
- 第六の習慣:相乗効果を発揮する
に従うことです。
第五の習慣:理解してから理解される
まず、第四の習慣と第五の習慣の順番を入れ替えたのは、相手のことを理解しないと、「Win-Winを考える」こともできないからです。
「第五の習慣:理解してから理解される」において、一番重要なポイントは、
・相手は、自分のことを理解されない限り、あなたに興味がない(興味が沸かない)

ということです。
あなたが、どれだけ素晴らしいアイデアをもち、どれだけ熱心にその良さを説明して、誰かを説得しようとしても、

この人は自分のことを全然理解してくれてないし、そんな熱心に説明されても、1mmも興味沸かへんわ、、、
となり、相手は、自分のことを理解してくれない人には、関心すら持ちません、、、

「あっ、この人は自分のことを理解してくれている!」「自分の考えや気持ちを尊重してくれている!!」
という思いが芽生えて、初めて、

自分のことをきちんと理解してくれてるし、ちょっと、話聞いてみよっかな!?
となります。

相手が、「自分のことをきちんと理解してくれている!」と思うまでは、何をどれだけ頑張って伝えても、相手の心には響きません、、、。 誰かと協力して何かに取り組む際には、「相手を理解すること」から始める必要があります!
第四の習慣:Win-Winを考える
「相手を理解すること」ができれば、次は、「Win-Winを考える」ことができます。
「Win-Winを考える」とは、
- お互いの期待値を知ること
- お互いにとって納得できる選択をすること
です。
まずは、「相手を理解すること」で、相手が
- 何を望んでいるのか?
- 何を大切だと考えているのか?
- どんなことに挑戦したいと思っているのか?
という期待値を正しく知ることが大切です。
プロジェクトにおいて、相手(各メンバー)の期待値を正しく知るには、
『6-4.プロジェクトを成功に導く秘訣(3)「決意表明と期待値の交換」を行う』の記事でもご紹介しているのですが、
プロジェクトの開始時に、メンバー全員に
- 本プロジェクトで挑戦したいこと
- 本プロジェクトで不安に感じていること
- 特に、周りのメンバーからサポートして欲しいこと
を発表してもらい、メンバー全員で認識を合わせると良いです。

そして、相手の期待値を正しく知ってから、

「自分自身の期待値と、どう折り合いをつけるか?」「どうすれば、お互いに納得ができるか?」
を考えて、十分に話し合い、お互いにとって納得できる選択をすることが大切です。

「Win-Winを考える」ためにも、相手を理解して、期待値を正しく知ることが必要不可欠です! 相手の期待値を正しく知ってこそ、自分の期待値と折り合いをつけて、お互いに納得できる選択をすることができるようになります!
第六の習慣:相乗効果を発揮する
「相手を理解すること」「Win-Winを考えること」を大前提として、更に、お互いにとって大きな成果を残すために必要なのが「相乗効果を発揮する」ことです。
「相乗効果を発揮する」とは、
- 「自分の案」と「相手の案」以外の「第三の案」を考えること
- 「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残すこと
です。
「相乗効果」を発揮して、「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残すためには、「自分の案」と「相手の案」を聞いたうえで(尊重したうえで)
「自分の案」と「相手の案」の枠を超えた「第三の案」を考える必要があります。
- 「自分の案」と「相手の案」のどちらを採用するか?
- どの部分とどの部分を組み合わせるか?
- どこを修正して、何を追加するか?
など、「自分の案」と「相手の案」だけの枠に捉われていると、より大きな成果を残すための発想ができなくなってしまいます、、、
「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残すためには、「自分の案」と「相手の案」の枠を超えた「大胆な発想」が必要であり、

「大胆な発想」には、必ずついてくるリスクを背負う覚悟も併せて求められます。

「相乗効果を発揮する」には、リスクを伴うので、スティーブン・R・コヴィー氏は、著書『7つの習慣』の中で、「すべての状況において、必ずしも相乗効果を発揮する必要はない」と述べています。

「相乗効果を発揮する」ことは、絶対じゃないんや!?
と思われたかもしれませんが、
「第五の習慣:理解してから理解される」「第四の習慣:Win-Winを考える」だけでも、複数人で効果的に協力し、あらゆる課題を解決して、ゴールを達成できることがほとんどです!
なぜ、『7つの習慣』に従うことが大切なのか?
なぜ、『7つの習慣』に従うことが大切なのか?というと、
- お互い理解し合わないと、Win-Winには成り得ないから
- Win-Winの関係でないと、中長期的な信頼関係を築けないから
- 中長期的な信頼関係こそが、お互いに利益をもたらすから
です。
お互い理解し合わないと、Win-Winには成り得ないから
複数人で協力し、課題を解決しながら、同じゴールを達成する活動(=プロジェクト)を行う場合、関係者間で、お互いが理解し合うことで、Win-Winの関係が成り立ちます。
Win-Winの関係には、お互いの理解を深めることが必要不可欠です。
そして、お互いの理解を深めるには、まずは、「相手を理解すること」が必要なので、プロジェクトを成功に導くには、関係者を理解することから始めることが大切です。

「関係者」には、一緒にプロジェクトを遂行する社内のメンバーだけではなく、お客様や協力会社様など、社内外含めたすべての利害関係者が含まれます。 すべての関係者のことを理解するのは大変ですが、それが成功への第一歩となります!
Win-Winの関係でないと、中長期的な信頼関係を築けないから
プロジェクトゴールを達成するために、プロジェクト期間中にWin-Winの関係を築くことは当然ですが、プロジェクトが終わった後も、関係者間でWin-Winの関係を維持することで、中長期的な信頼関係を築くことが可能です。

そして、Win-Winの関係ではない場合、中長期的な信頼関係を築くことはできません。
Win-Loseであっても、Lose-Winであっても(相手に常に勝たせてあげても、相手に常に勝っても)、もちろんLose-Lose(どちらにとっても不利益)であっても、
相手との中長期的な信頼関係は築けません。

Win-Winの関係だけが、相手との中長期的な信頼関係を築くことができ、一時的に、Win-Lose、もしくは、Lose-Winの関係になった場合は、必ず、次回は逆の関係になるように調整し、中長期的にWin-Winの関係を維持することが大切です!
中長期的な信頼関係こそが、お互いに利益をもたらすから
プロジェクト期間中はもちろん、プロジェクト期間後においても、Win-Winの関係を維持し、中長期的な信頼関係を築くことで、お互いに利益がもたらされます。
「お金の切れ目は、縁の切れ目」の言葉通り、
プロジェクト期間が完了したら関係が疎遠になってしまっている、、、
ことが多く、非常に残念に思います。
プロジェクト期間中に、苦楽を共にすることで、せっかく築くことができた信頼関係は、放っておけば、すぐにバラバラになります。
『4-18.ゴールの達成に集中する極意(16)「エントロピー増大の法則」を理解する』の記事でもご紹介しているのですが、
どんなものでも、秩序があるものは、放っておくと、無秩序な状態へと変化していきます。

プロジェクト期間中に、あれだけ強固な信頼関係を築くことが出来たから、私たちは大丈夫!!
ということは、ありません。
時間も、エネルギー(気力と体力)も、お金も何も投下しなければ、どんな信頼関係であっても、必ず、無秩序な状態に陥ります。(別に、放っておいても、憎しみ合う状態になる訳ではありませんが、相手に対する信頼は、必ず薄れていきます、、、)
中長期的な信頼関係があってこそ、お互いに利益(メリット)が生じるものです。
仕事を依頼した側(発注者側)は、プロジェクト期間内で、すべての要望を実現することは難しく、プロジェクト期間内で提供された建物やシステム、商品やサービスを使いこなして、更なる成長や発展を目指す必要があり、
更なる成長や発展には、関係者(特に、受注者側)の協力が必要不可欠です。
仕事を依頼された側(受注者側)は、プロジェクト期間内に提供した建物やシステム、商品やサービスを、お客様に、想定通りに、もしくは、想定以上に使って頂いて初めて、価値を提供できたことになり、
お客様が
- プロジェクト期間内に想定していたこと(想定以上のこと)を実現できたのか?
- 実現できていない場合は、何が原因で、どう改善すれば良いのか?
- 実現できていた場合は、更なる成長や発展のために、何ができるか?
ということを、きちんと確認し、改善点はすぐに修正し、更なる成長や発展に貢献することで、新しい仕事を依頼されることにも、自身の成長や発展にも繋がります。

お互いに中長期的な信頼関係を築くには、「エントロピー増大の法則」を理解したうえで、プロジェクトが完了した後も、意図的に、信頼関係を維持するために、時間やエネルギー(気力や体力)、お金を投下することが大切です!
どのように、『7つの習慣』に従うと良いのか?
どのように、『7つの習慣』に従うと良いのか?というと、
- 感情移入の傾聴を行う
- Win-Winにならない場合は、決断しない
- 相違点を喜ぶ
と良いです。
感情移入の傾聴を行う
「第五の習慣:理解してから理解される」において、まずは、「相手を理解すること」から始める必要がありますが、相手を理解するには、「感情移入の傾聴を行う」と良いです。
「感情移入の傾聴を行う」とは、
- 自分の主張を聞いて欲しいから、相手の話を聞くのではないこと
- 相手に誠実な関心を寄せて、相手の話を聞くこと
- 相手の感情までも理解すること
です。
自分の主張を聞いて欲しいから、相手の話を聞いている場合、(自分のことを理解して欲しいから、相手のことを仕方なく理解する場合)
その態度は、すぐに相手に伝わります。
例え、相手の話を聞いている素振りを見せても、相手は、

「あっ、この人は、自分の話にしか興味ない人だ、、、」「私の話は、聞き流しているだけだ、、、」「私の気持ちも、全然分かろうとしてくれない、、、」
と感じてしまい、心を閉ざしてしまいます。
相手の話を聞く際は、誠実な関心を寄せることです。

誠実な関心を寄せるということは、
- 相手に対して興味や関心があるから、話を聞く
- 私心(自分のことを理解して欲しいという気持ち)を捨てて、相手の話に100%集中して話を聞く
ということです。
そして、誠実な関心を寄せて話を聞くことで、相手の感情までも理解することが大切です。
話を聞く相手が、

「どんな気持ちで話してんのかな?」「一番伝えたいことは何なんやろ?」「結局、何を叶えたいと考えてんのかな?」
と考えながら話を聞いて、真意を汲み取り、それらを理解して、相手の主張や感情を代弁できるようになることが大切です。

自分の話を聞いて欲しいから、仕方なく相手の話を聞くのは、絶対NGで、そんな下心はすぐに見透かされてしまいます。相手に対して誠実な関心をもち、純粋に興味があるから話を聞き、相手の主張や感情を代弁できるまで聞くと良いです!
Win-Winにならない場合は、決断しない
「第四の習慣:Win-Winを考える」において、

毎回、いつもWin-Winの関係になるとは、限らないのでは、、、、?
と思われたかもしれませんが、
Win-Winの関係にならない場合、
- 一時的に、Win-Lose、もしくは、Lose-Winとなるなら、次回は逆の関係にすることで、中長期的にWin-Winの関係を築くようにする
- Win-Winにはどうしてもならないので、決断しない=何もしない
のどちらかを選択すると良いです。
中長期的にWin-Winの関係を築くことができるのであれば、一時的に、Win-Lose、もしくは、Lose-Winとなることを許容することができますが、
どうしても、Win-Winにならない場合は、決断しない=何もしない方が良いです。
実際に、冒頭で紹介した「次世代起業家・経営者アカデミー」の代表講師である加藤さんも
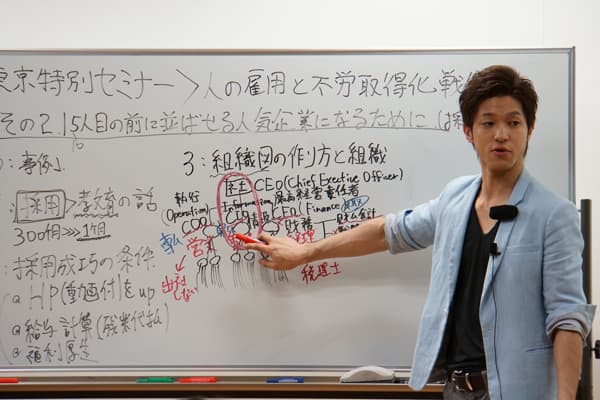
・Win-Winの関係にならないのに、情に流されて協業(人を採用)してもロクなことがない
と繰り返し注意喚起しています。
プロジェクトにおいても、課題の解決策を検討しており、Win-Winになるような解決策が見つからない場合は、ムリにやらない方が良いです。
協力してプロジェクトを進める関係者を探している際に、中長期的にWin-winの関係を築くことができないと判断した場合は、ムリに手を組まない方が良いです。
- 時間が無い、、、
- これ以上、良い解決策が思い浮かばない、、、
- 良いパートナーが全然見つからない、、、
- 経営層(社長や役員など)からの紹介なので、断りにくい、、、
など、Win-Winにならない場合でも、決断したい(何かをしたい)という場面があるかもしれませんが、Win-Winにならない以上、中長期的な信頼関係を築くことができないので、ムリに決断しても(何かをしても)良い成果は残せません、、、

「決断しなくては(何かをしなくては)、、、」という焦燥感を感じても、決断したい(何かをしたい)衝動を抑えて、グッと我慢して、Win-Winになる解決策やパートナーを探すか、その場は諦めて、決断しない(何もしない)ことが大切です!
相違点を喜ぶ
「第六の習慣:相乗効果を発揮する」には、「相違点(違い)を喜ぶ」ことが肝心です。
同じような意見や考え方では、「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残せるようなアイデアは生まれません。
意見や考え方に「違い」が合ってこそ、発言する価値のある意見や考え方となります。
誰かの顔色を気にしながら、その人の意見や考え方に同調しても、その意見や考え方に、新しい価値はありません。
「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残せるようなアイデアを生むには、「相違点(違い)を喜ぶこと」「相違点(違い)を歓迎すること」で、様々な意見や考え方を引き出し、リスクを背負うことは覚悟のうえで、大胆な発想を促す必要があります。
経験が少ない人、若い人ほど、その会社、その業界に対する慣習に染まっていないので、大胆な発想ができるものですので、経験が少ない人、若い人の突拍子もない意見や考え方に対して、

何を言うてんねん!? そんなん(業界の常識的に考えて)アカンに決まっているやろ!!
と否定するのではなく、

(今までの常識から言ったら、ありえへんけど)そんな考え方あるんか!? なになに、もうちょっと、何でそう考えたか教えて!!

というように、違いを歓迎して、
経験が少ない人、若い人からの突拍子もない意見や考え方に、経験豊富な人、ベテランの知見やノウハウを付け加えながら、「1 + 1 」が「3以上になる」成果を残せるような新しいアイデアを生むことが大切です。

「知識や経験はあればあるほど良い」と思われがちですが、これまでの常識を覆すような新しいアイデアを生む際には、邪魔になることもあるので、経験が少ない人や若い人の業界の常識ではありえないような意見や考え方も大切になります!
まとめ
- 複数人で効果的に協力し、あらゆる課題を解決して、ゴールを達成するカギになる「第五の習慣:理解してから理解される」「第四の習慣:Win-Winを考える」「第六の習慣:相乗効果を発揮する」に従い、プロジェクトを進めること
- 何よりもまず、「相手を理解すること」から始めること
- 相手を理解して初めて、「Win-Winを考える」ことも「相乗効果を発揮する」こともできること
複数人で協力して同じゴールを目指す際は、何よりもまず、「相手を理解すること」から始め、「Win-Winを考える」こと「相乗効果を発揮する」ことで、
プロジェクト期間中はもちろん、プロジェクト後も、関係者と中長期的な信頼関係を築き、あなたの人生がより良いものになることを、心から願っています!