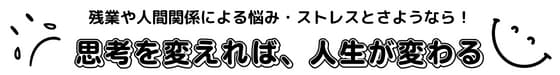『6-17.プロジェクトを成功に導く秘訣(16)すべての情報をすぐ使えるようにする』の記事では、
- 情報を分かり易く整理し、最新状態に保ち、関係者間で共有することで、プロジェクトの関係者全員が、欲しい情報をすぐ使えるようにして欲しいこと
- 「すべての情報をすぐ使えるようにする」ために、情報を階層化して整理し、時系列に沿って並べて、「同じ情報か?」をすぐに確認できるようにして欲しいこと
をお伝えしました。
今回の記事も含めて、具体的に『プロジェクトを成功に導く秘訣』について、詳しく解説しますので、あなたが日常生活で、仕事をするうえで、「使える!」と思ったものは、どんどん実践してみてください!
『プロジェクトを成功に導く秘訣』の17個目は、
・「スコープ」を曖昧にしない
です。

「スコープ」とは、「プロジェクトの範囲」のことで、「プロジェクトの範囲」とは、今回のプロジェクトの「期間」と「コスト」の中で、「どこまでの要件を実現するのか?」「どの範囲まで作業を行うのか?」「やるのか?やらないのか?」を関係者で明確に決めることになります!
「スコープ」を曖昧にしないとは?
「スコープ」を曖昧にしないとは、
今回のプロジェクトの範囲内(「期間」と「コスト」の中)で、
- 「やる」「やらない」をハッキリすること
- 「できないことは、できない」と伝えること
です。そして、
- 「やらない」「できない」は、無責任ではない
です。
「やる」「やらない」をハッキリすること
プロジェクトでは、定められた「期間」と「予算」があり、その中で、プロジェクトゴールを達成する必要があります。
「期間」と「予算」以外にも、プロジェクトに参加できる「人」にも制限がある場合もあります。
また、他にも
- 現在の技術では、実現ができないこと(実現が非常に難しいこと)
- 実現するには、「期間」も「コスト」も掛かり過ぎること
- 実現出来たとしても、現場が混乱する恐れのあるもの(動作が不安定など)
など、様々な制約がある中で、プロジェクトゴールの達成方法を模索しなければなりません。
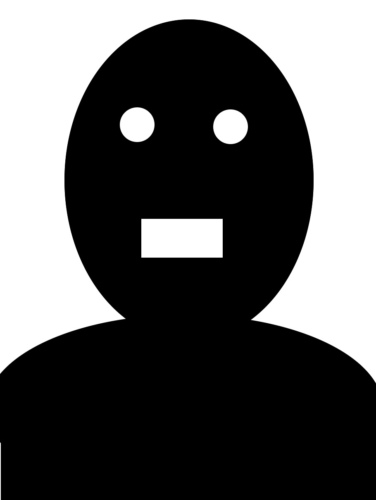
そうは言っても、せっかくプロジェクトをやるなら、プロジェクトゴールに要件を詰め込めるだけ、詰め込みたいやん!?
と思われたかもしれませんが、
一つのプロジェクト内で、ありとあらゆる要件を実現するのは、不可能です。
「期間」や「予算」、「人」や「技術力」など、様々な制約がある中で、今回のプロジェクトでは、
- 絶対に達成したいことは何なのか?
- どこまでの要件を実現するのか?
- どの範囲まで作業を行うのか?
を決める必要があります。
プロジェクトの関係者で、「やる」「やらない」をハッキリして、合意することが大切ですが、
特に、曖昧になりがちな「やらない」ことをハッキリして、合意することが大切です。

日本人の性格(日本の文化?)なのかもしれませんが、「やらない」ことの方が、「やる」ことよりも合意するのが断然難しいです! 「やる」ことは合意せずにやっても許されます(プラスαのサービスは喜ばれます)が、「やらない」ことは絶対に合意しておかなければいけません!
「できないことは、できない」と伝えること
「やらない」ことをハッキリして、合意するためには、「できないことは、できない」と伝える必要があります。
基本的に、お客様(発注者側)からの要望に対して、「できない」ことを伝えるのは、仕事を請ける側(受注者側)となり、
通常は、お金を受け取る側(受注者側)の方が立場が弱いものなので、(対価をもらえなければ困るからですね、、、)
「できない」と伝えるのは、言いにくいものですが、「できないことは、できない」と伝え、プロジェクトの範囲から外すことが大切です。
「できない」ことを伝えると、

(発注者側)
「なんで、できへんの?」「ほんまに、できへんの?」「どうしても、できへんの!?」
など、お客様側(発注者側)から、鋭い質問がくることになりますが、「できないことは、できない」ので、そこは曖昧にしてはいけません。

通常、お金を受け取る側(受注者側)の方が立場が弱いものなので、「できない」ことを伝えるのは勇気がいるものですが、そこは、勇気を振り絞って「できない」と伝えるか、上長などを使ってでも「できない」ことを伝えた方が良いです!
「やらない」「できない」は、無責任ではない
今回のプロジェクトの範囲において、「やらない」「できない」と言うことは、決して無責任なことではありません。
何かに対して「やらない」「できない」と言うことは、裏を返せば、「やる」「できる」と言ったことは、責任を持って必ずやりきることになります。
「やる、やらない」「できる、できない」を曖昧にして、
- 一体何をやるのか? (範囲、広さの問題)
- どこまでやるのか? (程度、深さの問題)
が不明確な状態でプロジェクトを進める方が危険です!

「やる、やらない」「できる、できない」を明確にして、「やらない」「できない」ことはやむを得ないとしても、「やる」「できる」と言ったことは、「期限内」「コスト内」に責任を持って必ずやりきることが大切です!
なぜ、「スコープ」を曖昧にしないことが大切なのか?
なぜ、「スコープ」を曖昧にしないことが大切なのか?というと、
- 「スコープ」を曖昧にすると、後から必ずモメるから
- 曖昧な返事は、相手にとっても迷惑だから
- 「やらない」「できない」が信頼につながるから
です。
「スコープ」を曖昧にすると、後から必ずモメるから
プロジェクトの範囲内において、「やる、やらない」「できる、できない」を曖昧にすると、後から必ずモメることになります。
お客様側(発注者側)が期待していたものと、仕事を請けた側(受注者側)が提供したものに、差異があった場合は、後から必ずモメることになり、一番多いケースが、
お客様側(発注者側)としたら、

(発注者側)
「やってくれるって言ってたやん!」「できるって言うたやん!!」
となり、仕事を請けた側(受注者側)としたら、
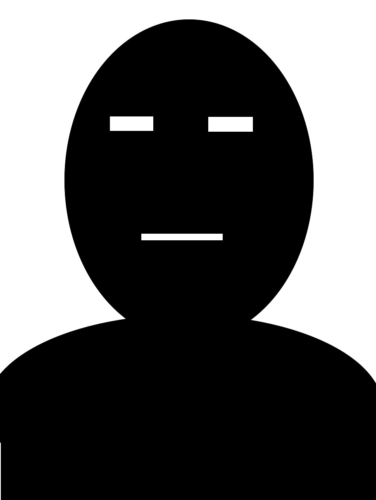
(受注者側)
「いや、やるとは言ってなくて、善処しますと伝えただけですが、、、」「必ずできるとまでは、言ってないんですが、、、」
となる状態です。
仕事を請けた側(受注者側)が
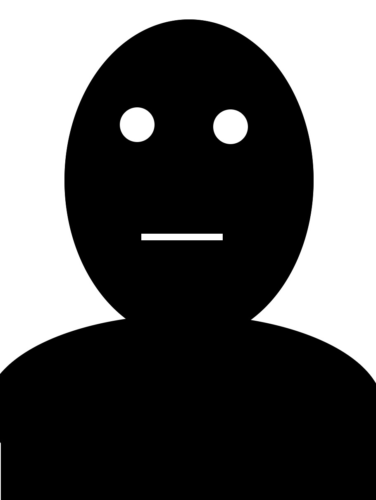
(受注者側)
「これは、ムリやな、、、」「十中八九できないやろな、、、」
と心の中で思いながらも、その場をしのぐために、

(受注者側)
「善処します!」「やれるだけやってみます!」「できるとこまでやります!!」
など、「何をどこまでやるのか?」「できるのか?できないのか?」を曖昧なままにすることが、
お客様側(発注者側)の期待値と、仕事を請けた側(受注者側)の提供物に差異が生じる一番の原因となります。

仮に、「善処します」「一度、検討します」などと回答した場合でも、後から、できないことが判明した場合は、「できない」ことを伝え、「何をどこまでやるのか?」を明確にして、お客様側(発注者側)と合意することが大切です。
曖昧な返事は、相手にとっても迷惑だから
これは、『4-3.ゴールの達成に集中する極意(2)爽やかにハッキリと断る』の記事でも書いているのですが、
・曖昧な返事は、相手にとっても迷惑
となります。
曖昧な返事をして、相手に変な期待を持たせること、相手の決断の時間を遅らせることは、相手にとっても迷惑となります。
- やるならやる(できるならできる)
- やらないならやらない(できないならできない)
とハッキリ伝えた方が、相手側も変な期待を持たずに済みますし、キッパリ諦めて、別の手段、別のアイデアを考えることができるようになります。

「やる」「やらない」、「できる」「できない」をすぐに決断できない場合は、期限を決めて検討することが重要で、一番ダメなのは、期限も決めずいつまでも決断を先延ばしにして、結局、最後に「やらない」「できない」と伝えることです!
「やらない」「できない」が信頼につながるから
「やらない」「できない」と言うことは、言いづらいもので(特に、日本人は断るのが苦手なので、、、)、一時的に(その場では)険悪な雰囲気になる場合もありますが、
中長期的な視点で見ると、「やらない」「できない」とハッキリ伝え、しかし、「やる」「できる」と言ったことを必ずやりきる方が、信頼関係を構築できます。
ビジネスでは(ビジネスだけではないですが、)言ったことを必ずやる人が信頼されます。

「あの人は、言ったことは必ずやってくれる!」「あの人が、やる!できる!と言ったなら、大丈夫やわ!!」
と思われることが、信頼されるということです。

逆に、「やります!」「できます!」と気前よく仕事を請けておいて、結果的に「ごめんなさい!やれません(できません)でした、、、」と言って、お客様の期待を裏切ることは、信頼を失う行為となります!
どのように、「スコープ」を曖昧にしないと良いのか?
どのように、「スコープ」を曖昧にしないと良いのか?というと、
- 「やらない」「できない」は当然のことと理解する
- 「やらない」「できない」理由を明確にする
- 「やらない」「できない」は永遠ではないと伝える
と良いです。
「やらない」「できない」は当然のことと理解する
上述した通り、プロジェクトには、「期間」や「予算」、「人」や「技術力」など、様々な制約があるので、すべての要件を実現するのは、不可能です。
もちろん、「少しでもお客様(発注者側)を満足させたい!」という気持ちは、すべての仕事を請ける側(受注者側)が持っているものですが、(たぶん、、、。少なくも私は、、、)
何かに対して、「やらない」「できない」と言わなければならないのは、当然のことであり、
何かに対して、「やらない」「できない」と言った代わりに、「やる」「できる」と言ったものは、責任をもって必ずやりきることが大切です!
すべての要件を実現するのは、不可能なので、
- どの要件を実現することが、お客様にとって一番有益か?
- どのように要件に優先順位をつければ、関係者が一番納得できるか?
- 要件を少しでも多く実現するには、どのように取捨選択すれば良いか?
ということを、真剣に考えて、検討に検討を重ねて、要件を絞り込みます。
「やらない」「できない」ことが発生するのは、当然のことと理解したうえで、要件に優先順位をつけて、お客様に最大の価値を提供できるようにすることが大切です。

「やらない」「できない」ことがあるからこそ、「やる」「できる」ことに対して真剣に取り組むことができますし、何を「やる」「できる」ことが一番良いのか?を真剣に考えることができるようになります!
「やらない」「できない」理由を明確にする
「やらない」「できない」ことを伝える際は、必ず、「やらない」「できない」理由を明確にして、お客様にも納得してもらう必要があります。
- なぜ、「やらない」のか? なぜ、「できない」のか?
- 「期間」「コスト」「人」「技術力」など、どこに問題があるのか?
- 「やらない」「できない」場合、どのような影響があり、どう対処するのか?
- どのような条件であれば、「やる」「できる」可能性があるのか?
など、お客様に納得して頂けるまで、「やらない」「できない」理由を丁寧に説明することが大切です。
「やらない」「できない」理由を納得してもらえないということは、「やる」方が良い、「できる」かもしれないということなので、
- 本当に「やらない」方が良いのか?
- どうしても「できない」のか?
を再検討する必要があります。

「やらない」「できない」理由を納得して頂くこと、「やる、やらない」「できる、できない」をハッキリさせることは、時間もエネルギー(気力と体力)も必要ですが、根気強くお互いが納得できるまで議論することが大切です!
「やらない」「できない」は永遠ではないと伝える
「やらない」「できない」理由を明確にした後、「やらない」「できない」ことは、この先もずっと「やらない」「できない」ことではないと、お客様に伝えることが大切です。
「やらない」「できない」理由が解消されれば、その瞬間から「やる」「できる」に変わります。
今回のプロジェクトの範囲内では、「期間」や「コスト」、「人」や「技術力」などの制約があってやらない、できないものも、
「やらない」「できない」理由が、次回のプロジェクトまでに解消されていれば、「やる」「できる」ことになります。

今回のプロジェクトの範囲内では、「やらない」「できない」ことも、その理由をお客様と一緒に解消していくことで、中長期的に、お客様の期待や要望に応えていくことが大切で、「やらない」「できない」をそのまま放置してはダメです!
まとめ
- 今回のプロジェクトの範囲内で、「やる、やらない」「できる、できない」をハッキリさせて、関係者間で合意すること
- 曖昧な返事は、相手にとっても迷惑であること
- 「やらない」「できない」理由を明確にして、その理由を協力して解消していくこと
プロジェクトを進めていくなかで、「やる、やらない」「できる、できない」の議論は必ず起こり、曖昧なままにしておくと、必ず後からモメることになります。
「やる、やらない」「できる、できない」をハッキリさせて、関係者間で合意することで、期待通りのものを必ず提供し、中長期的な信頼関係を築いていけるようなることで、あなたの人生がより良いものになることを、心から願っています!