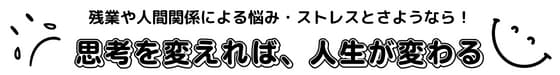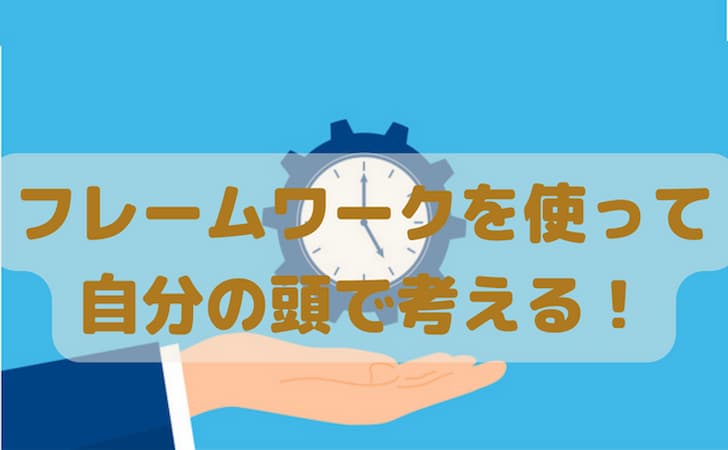『5-10.短時間で成果を残す原則(9)周りを「デキる人」で固める』の記事では、
- あなたの周りを、仕事が「デキる人」=お客様に対する「価値提供能力が高い人」で固めて、仕事の質とスピードを圧倒的に向上させて欲しいこと
- お客様に対する「価値提供能力が高い人」を見極めて、信頼関係を築き、他の誰にも邪魔されないように、「デキる人」との仕事でスケジュールを埋め尽くして欲しいこと
をお伝えしました。
今回も含めて複数の記事で、具体的に『短時間で成果を残す原則』について、詳しく解説しますので、あなたが日常生活で、仕事をするうえで、「使える!」と思ったものは、どんどん実践してみてください!
『短時間で成果を残す原則』の10個目は、
・便利なフレームワークを利用する
です。

インターネットを使ってちょっと調べるだけで、世の中には、分析や検討を行う際に使える、とても便利なフレームワーク(思考の枠組み)がゴロゴロ落ちています。たくさんの種類があり、更には、具体的な実例まで載っていたりするので、これらを使わない手はありません!
目次
「便利なフレームワークを利用する」とは?
「便利なフレームワークを利用する」とは、
何かの分析や検討を行う際に、
- ゼロから自分で考えるのではなく、便利な思考の枠組みを利用する
ということです。
ゼロから自分で考えるのではなく、便利な思考の枠組みを利用する
何かの分析や検討を行う際に、
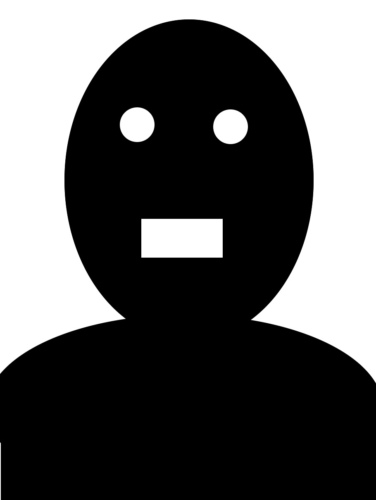
ゼロから自分の頭で考えなくても良いの!?
と思われたかもしれませんが、
世の中には、既に似たような分析や検討を行った人がいて、
インターネットを使ってちょっと調べるだけで、これから分析や検討を行う際に使える、便利なフレームワーク(思考の枠組み)が、たくさん掲載されています。
インターネットだけでなく、書籍としても、ビジネスの様々な場面で使えるフレームワーク(思考の枠組み)をまとめたようなものがたくさん販売されています。
例えば、大きな視点(マクロな視点)で、企業経営の前提条件を分析するためのPEST分析、
- 政治(Politics):政府は今後どのような施策を打ち出し、法律はどう変わるのか?
- 経済(Economy):経済状況はどうなるのか? 景気はどうなるのか?
- 技術(Technology):どのような技術革新が、どのタイミングで起こるのか?
- 社会(Society):これからどんな社会になり、どのような価値観が普及するのか?
上記4つの要素をそれぞれ分析したうえで、今後、企業の戦略や組織体制をどうするのか?を検討し、実行する
企業がもつ、経営資源を分析し、競争優位性を獲得するためのVRIO、
- 経済価値(Value):市場(お客様)に対して価値を提供できる経営資源は何か?
- 希少性(Rarity):他の企業がもっていないような希少性がある経営資源は何か?
- 模倣困難性(Imitability):他社が模倣することが困難である経営資源は何か?
- 組織(Organization):上記3つの経営資源を活用できる組織になっているか?
上記4つの視点で、企業を分析し、どのような組織体制で、どの経営資源に注力し、どの経営資源を更に伸ばしていくことで、競争優位性を維持・向上できるか?検討し、実行する
企業が成長する方向性を検討するための、アンゾフの事業拡大マトリクス、
- 市場浸透:既存市場に既存製品を販売し、市場シェアの拡大、売上(利益)拡大を目指す
- 新製品開発:既存市場に新規製品を販売することで、売上(利益)拡大を目指す
- 新市場開拓:既存製品を新規市場に販売することで、売上(利益)拡大を目指す
- 多角化:新規製品を新規市場に販売することで、売上(利益)拡大を目指す(難易度:高)
今後、企業がどのように成長するのか?上記4つの中から最適な方向性を選択し、実行する
などがあります。
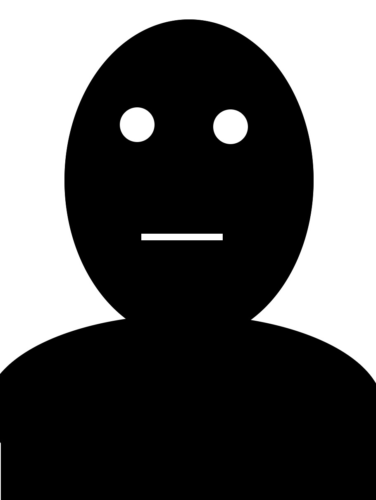
これから、どのような観点や切り口で、分析や検討を行えば良いか、、、?
というように、すべてをゼロから自分の頭で考えていると、時間がいくらあっても足りないので、
既に世の中で使われており、その有効性が認められている便利なフレームワーク(思考の枠組み)に沿って、自分の頭で考えることが大切です!

ご紹介したものは、本当に代表的な一例で、何を分析・検討するかによって、使えるフレームワーク(思考の枠組み)は異なりますので、その都度、一番便利で使えるフレームワーク(思考の枠組み)を利用するのがオススメです!
私は、いつでも、便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用できるように、ビジネスで使える基本フレームワークがまとまった書籍を、ずっとカバンに忍ばせています!
なぜ、「便利なフレームワークを利用する」ことが大切なのか?
なぜ、「便利なフレームワークを利用する」ことが大切なのか?というと、
- 抜け漏れがなく、質の高い(要点を抑えた)分析・検討が可能だから
- 分析・検討結果を、複数人で共通認識として共有することができるから
です。
抜け漏れがなく、質の高い(要点を抑えた)分析・検討が可能だから
「便利なフレームワークを利用する」ことで、フレークワーク(思考の枠組み)に沿って、分析・検討するだけで、抜け漏れがなく、質の高い(要点を抑えた)分析・検討が可能になります。
便利なフレームワーク(思考の枠組み)は、

「このテーマの分析・検討する際は、この点を絶対に抑えておいた方が良い!」
という、多くの先人の方々の実践と経験によって磨き上げられた先人の知恵が詰め込まれたものなので、
便利なフレームワーク(思考の枠組み)を残してくれた先人の方々に感謝して、あとは、思う存分、使い倒すのが良いです。
多くの時間とエネルギー(気力と体力)をかけて、先人の方々が残してくれた便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用して、
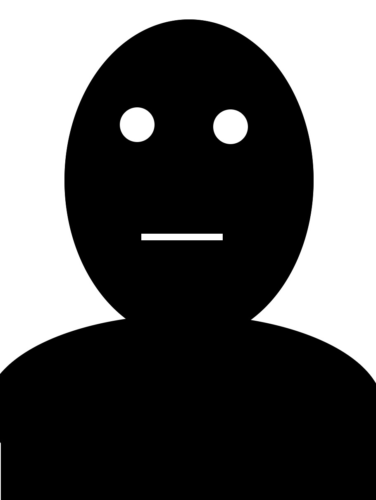
自分たちだけ、短時間で成果を残してしまって、良いんかな、、、?
と、少し申し訳ない気持ちをもたれたかもしれませんが、
そんなことは、気にしたら負けです(笑)

世の中に公開されていて、便利で使えるものは、遠慮なくどんどん使い倒してください! 私は、少し申し訳ないと思う分だけ、先人の方々に「こんな素敵なフレームワーク(思考の枠組み)を残してくれて、本当にありがとう!」と心から感謝するようにしています!
分析・検討結果を、複数人で共通認識として共有することができるから
また、複数人で仕事をする際は、便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用して行った分析・検討結果を、必ず、共通認識として共有することが大切です。
- 各自が行った分析・検討結果を共有して、複数人でブラッシュアップする
- 初めから複数人で行った分析・検討結果を、更に別の人に共有して、指摘をもらい改善していく
など、便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用して行った分析・検討結果をより多くの人に見せて、改善し、磨きをかけ、共通認識として共有することで、同じ方向を向いて、同じところを目指して仕事をすることが重要です。
ぜひ、分析・検討結果を自分だけ、自部門だけに留めておくのではなく、他人に、他部門に見せることで、分析・検討結果を改善し、磨きをかけるようにしてください!
分析・検討結果を他人や他部門に見せると、
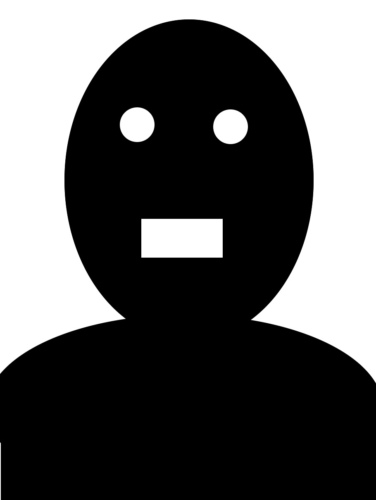
他部門
「それ、考え方が全然違うわ!」「もっと、こうした方が良いと思うけどな、、、」「こうした方が、絶対に腹落ちできるわ!!」
など、同じ会社内であっても、部門が異なれば、意見や考え方は異なるものなので、確実に色々言われます(泣)

しかし、価値を提供すべきお客様は共通で、売上(利益)を伸ばし、会社をより良いものにしたいというゴールも同じなので、異なる意見や考え方を取り入れながら、分析・検討結果を改善し、会社としての共通認識として共有することで、同じ方向を向いて、同じところを目指して仕事をすることが大切です!
どのように、「便利なフレームワークを利用する」と良いのか?
どのように、「便利なフレームワークを利用する」と良いのか?について、
- お客様が商品やサービスのことを知り、情報を調べ、比較検討しながら、実際に購入し、更には継続利用してもらえるまでの体験を分析・検討する「カスタマージャーニーマップ」
という便利なフレームワーク(思考の枠組み)を具体例にして、解説していきます。
【具体例】「カスタマージャーニーマップ」
業界や業種によって、お客様が商品やサービスを知り、継続利用するまでのプロセスは様々で、「カスタマージャーニーマップ」も、業界や業種によって色々カスタマイズされていますが、
ここでは、多くの業界や業種でも共通している購買プロセスである
- 認知・興味関心:お客様が商品やサービスのことを知り、興味や関心を持つ段階
- 情報収集:興味や関心をもった商品やサービスについて、より詳細な情報を調べる段階
- 比較検討:最終候補を複数に絞り、どれを購入・導入するか?比較検討する段階
- 購入・導入:購入・導入を決定し、商品やサービスを利用可能な状態にする段階
- 継続利用:購入・導入した商品やサービスに満足し、継続して利用する段階
の5つのステップについて、以前私が携わっていた「防災無線システム」を具体例にして、解説します。
「カスタマージャーニーマップ」を作成する際は、
まずは、「お客様がどのような人物かを明らかにする」必要がありますが、「防災無線システム」の場合は、「各自治体(特に、市町村)の防災担当者様」がお客様となります。
※「防災無線システム」とは、各自治体の防災担当者の方々が、台風や地震、津波などの災害に対して、防災用の無線機とスピーカーを使って、避難や注意を呼びかけることで、住民の方々に少しでも安全を確保して頂くためのシステムです。
そして、各購買プロセスにおいて、
- お客様が、どんな考えや気持ちをもち、
- お客様と、どこでコンタクトをとり、何を伝えるのか?(何を行うのか?)
- お客様に、次のステップに移ってもらうには、どうすれば良いのか?
を一つずつ、分析・検討していきます。
認知・興味関心フェーズ
防災無線システムの例では、
- お客様の考えや気持ち:最近、台風や大雨などの自然災害が猛威を奮っている、、、。防災対策を強化・見直ししなければ、、、
- コンタクト場所と実施内容:各自治体の防災担当者様が多く参加する展示会へ出展し、防災対策の強化・見直しには、防災無線システムが最適であることをお伝えする
- 次のステップへの移行手段:各自治体(特に、市町村)の防災担当者様と連絡先を交換し、初回訪問の約束をする
となります。
認知・興味関心フェーズでは、とにかく、お客様に知って頂き、興味・関心を持ってもらうことが大切です。
展示会への出展、セミナーの開催、各種メディアへの広告出稿など、知ってもらう手段は様々ですが、「お客様がどこにいるのか?」を正確に把握し、確実にお客様に知ってもらうこと、
また、投資対効果が高い手段を採用することがポイントです。
投資対効果 = (得られた利益)÷(かかったコスト)× 100 (%)
であり、
(展示会、セミナー、広告をきっかけに受注できた仕事から得られる総利益)÷(かかったコスト)×100(%)
として算出することが可能です。

投資対効果を比較することで、「展示会に出展するのが良いのか?」「セミナーを開催するのが良いのか?」それとも「広告への出稿が良いのか?」など実施した様々な施策の中から、一番良い施策を選別することができます!
情報収集フェーズ
防災無線システムの例では、
- お客様の考えや気持ち:防災対策の強化・見直しには、防災無線システムが良さそうだが、どんな仕様で、どのぐらいの導入期間とコストが必要なのか、詳細を知りたい、、、
- コンタクト場所と実施内容:お客様先へ訪問を行い、防災無線システムの仕様、導入期間、コストなど、詳細な情報をお伝えする。また、必要に応じて、デモも実施する
- 次のステップへの移行手段:各自治体(特に、市町村)の防災担当者様が、防災無線システムを新規導入・入替するのに必要な情報をすべてお伝えし、最終候補に選んで頂く
となります。
情報収集フェーズでは、可能であれば、直接訪問し、自社の商品やサービスの詳細をお伝えできれば一番良いですが、(それが一番確実で、一番正確に伝わるので。もちろん、遠隔でのお打ち合わせでもOKです)
最近は、お客様が自らインターネットを使ってWebサイトなどから情報収集するのが当たり前になっています。

お客様が自社のWebサイトなどからでも詳細な情報を分かり易く調べられるように、情報を事前に準備しておくことが大切です。 現在は、Webサイトに限らず、SNSなども利用して情報収集されるので、幅広い情報発信が求められます!
比較検討フェーズ
防災無線システムの例では、
- お客様の考えや気持ち:防災無線システムを提供可能な複数の会社を最終候補に絞ったが、どのような基準で、何を決め手として、最後の1社を決定しようか、、、
- コンタクト場所と実施内容:お客様先で開催される最終選考に参加し、防災無線システムの強みや独自性、実績、導入計画、運用保守体制などを、要点を絞ってお伝えする
- 次のステップへの移行手段:各自治体(特に、市町村)の選考基準を満たし、なおかつ、競合他社を上回る提案をすることで、最後の一社に決めて頂く
となります。
比較検討フェーズでは、最終選考が行われ、最終候補の中から、最後の一社が選ばれます。
自治体では、「求める仕様を満たす製品やサービスの中で、一番価格の安いものを選ぶ」競争入札という最終選考の方法があり、競争入札の場合は、価格だけで決まるので、提案を工夫する余地がありませんが、
「求める仕様を満たす製品やサービスについての提案を求め、提案内容、実績、実施計画、運用保守体制なども含め、総合的に優れていると判断したものを選ぶ」プロポーザルという最終選考の方法では、
「どのような提案ができるか?」で最後の一社に選ばれるか否かが分かれます。
プロポーザル形式で最終選考が行われる場合は、
- まずは、選考基準を必ず満たすこと
- 次に、独自性をアピールすることで、競合他社を上回ること
が大切です。
プロポーザル形式で最終選考が行われる場合は、基本的に「この項目について、提案して欲しい」という選考基準が明示されるものですので、
まずは、選考基準を必ず満たす(聞かれている項目に対して、必ず、回答する)ことを大前提に提案書を作成します。
次に、選考基準を満たす(聞かれている項目に回答する)だけでは、競合他社と差がつきませんので、独自性をアピールすることが重要です。
「何が独自性となるか?」は、各社によってそれぞれで、
- 他社にはない機能をもっている
- 導入実績が一番多い
- 運用保守体制が一番充実している(緊急時の受付体制があり、いつでも、すぐに、サポート可能な状態である)
- エンジニアのスキルが高い(高度な資格保有者の在籍数が多い)
など、独自性をアピールすることで、

「どこも似たり寄ったりの提案だから、価格の安いとこを選ぶか、、、」
と思われないようにすることが重要で、

「この機能もっているのは、この会社だけか!?」「実績が一番多いとこは、やはり信頼できるな!」「運用保守の体制が充実してて、いつでもすぐに対応してもらえるのはデカいな!!」
など、競合他社と単純な価格だけの比較にならないようにする工夫が必要です。

プロポーザル形式で最終選考が行われる場合、まずは、選考基準を満たさないと話にならないですが、やはり重要なのは「独自性」を強くアピールすることです! 競合他社と比較できないような「独自性」は、多ければ多いほど良いです!
購入・導入フェーズ
防災無線システムの例では、
- お客様の考えや気持ち:最終決定した最後の一社と速やかに契約を締結し、防災無線システムを指定した期日通りに(可能であればもっと早く)使える状態にしてもらおう!
- コンタクト場所と実施内容:お客様先で契約を締結し、事前に提案した通りの機能や品質、期日、金額で、防災無線システムを導入し、お客様に使って頂ける状態にする
- 次のステップへの移行手段:継続利用して頂くためにも、トラブルなく、約束した通りの機能、期日、金額で防災無線システムを導入し、導入を通じてお客様と信頼関係を築く
となります。
購入・導入フェーズでは、「商品やサービスを、実際に、お客様に使って頂ける状態にする」ことが最大の目的で、事前の期待にきっちり応えることが必要不可欠です。
一度、購入・導入して頂いた商品やサービスを、二度、三度と継続利用して頂くには、商品やサービスを購入・導入する前にもっていた、事前の期待にきっちり応える必要があり、
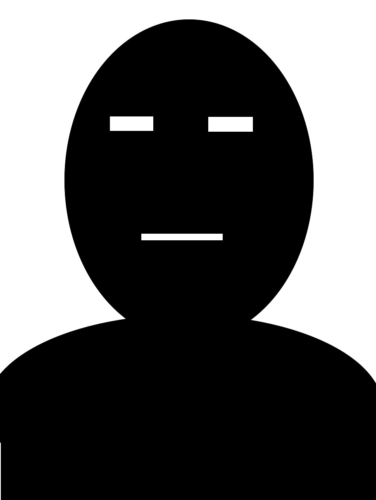
この商品(サービス)は、全然、想像していたのと違ったな、、、(もちろん、悪い意味で!)
などと思われてしまった場合、
お客様が、事前の期待を裏切られた商品やサービスを、再び購入・導入することはありません。
システム導入など、中長期間のプロジェクトとなる場合は、(長ければ数年単位ということもあります)
事前の期待にきっちり応える=約束した機能や品質、期日、コストを実現するには、プロジェクト管理を徹底して行う必要があり、プロジェクト途中で発生する様々な課題に、お客様と協力しながら解決していく必要があります。
大きなプロジェクトであればあるほど、(システム規模が大きい、期間が長いなど)約束した機能や品質、期日、コストをきっちり守ることは難しく、多くの課題を解決しなければなりませんが、
その分だけ、プロジェクトを通じて協力し合うことで、そして、事前の期待にきっちり応えることで、お客様との信頼関係を築くことが可能です。

事前の期待にきっちり応える=約束した機能や品質、期日、コストを実現することは、容易ではないですが、お客様と苦楽をともにして、それを一緒に乗り越えることで信頼関係を構築できれば、商品やサービスを継続利用してもらえます!
継続利用フェーズ
防災無線システムの例では、
- お客様の考えや気持ち:防災無線システムを使うことで、日々の防災活動に大いに役立っている。防災対策も強化できた。運用保守体制もしっかりしているし、次も依頼しよう!
- コンタクト場所と実施内容:お客様先にて、防災無線システムの定期的なメンテナンスを行う。また、システムに対する機能追加や改善のご要望には、速やかに対応する
- 次のステップへの移行手段:定期的なメンテナンスと、システムの更なる機能追加、品質向上により、お客様を最高に満足させ続けることで、次の仕事の依頼も頂く
となります。
継続利用フェーズでは、お客様を最高に満足させ続けることが大切で、お客様を最高に満足させ続けることで、次の仕事の依頼も頂けるようになります。
「売ったら終わり」という行為は、一瞬で、お客様との信頼関係が崩壊するので、必ず、継続的に、

「お客様が商品やサービスを問題なく使えているか?」「新しい課題は発生していないか?」「よりお客様を満足させるには、どうすれば良いか?」
を考えて行動し、お客様との信頼関係を中長期的に築いていくことが大切です!

プライベートでは、「結婚してからが、本当のスタート」であるのと同様に、ビジネスでは、「購入・導入してもらってからが、本当のスタート」になりますので、購入・導入してもらったお客様を最高に満足させ続けることが大切です!
まとめ
- 「便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用する」ことで、抜け漏れがなく、質の高い(要点を抑えた)分析・検討がより短時間でできること
- 分析・検討結果を、複数人で共通認識として共有することで、同じ方向を向いて、同じところを目指して仕事ができること
「便利なフレームワーク(思考の枠組み)を利用する」ことで、抜け漏れがなく、質の高い(要点を抑えた)分析・検討がより短時間でできるようになり、
更に、分析・検討結果を、複数人で共通認識として共有し、同じ方向を向いて、同じところを目指して仕事ができるようになることで、あなたの人生がより良いものになることを、心から願っています!